「何者なんだよ、そいつら。」
「わかりません。この銀河系には、666ほどの宇宙人がいますが、そのどれにも該当しません。」
「666!?」
「おそらく外宇宙からワープを使って来た可能性があります。」
「ヤバ!!ワープ!!」
「しかし、長距離のワープには、それなりの媒介装置が必要になります。ピラミッドのような、巨大な転送装置です。」

『ダンダダン』桃とセルポ星人の会話です。
♦1700年続いた村から、次の時代へ
青森県青森市にある「三内丸山遺跡」は、約1,700年続いた「縄文時代最大の遺跡」です。
私は、1,700年も村が続いていた事に、驚きました。
現在から1,700年前の時代は、どの時代になると思いますか?
戦国時代でしょうか?鎌倉時代でしょうか?否、平安時代でしょうか?
驚くべきことに、現在から1,700年前の時代は、弥生時代です。
弥生時代から現在まで、同じ場所に、同じ村が存続していたという事実は、大きな驚きです。
学校で教わる日本史は、何故か「稲作文化」に重点を置きます。
その為、縄文時代はスルーされ、弥生時代から本格的な説明がされる事が多いです。
そして、長い間、青森県を含む東北地方には「弥生時代はなかった」つまり「稲作文化は伝わっていなかった」と考えられてきました。
紀元前4世紀頃、朝鮮半島や中国大陸から、稲作が、北九州にもたらされました。
北九州にもたらされた稲作は、徐々に、西日本や東日本へと、伝播していきます。
★狩猟採集から農耕を基本とする社会へと変容していく
これにより、日本は、狩猟採集を中心とする社会から、農耕を中心とする社会に、変容していきます。
これが「弥生時代」の到来です。
ちなみに「弥生時代」という名は、東京都文京区弥生地区で発見された土器が「弥生式土器」と名付けられ、その時代に使われていた土器という事から「弥生時代」と名付けられました。
しかし、当時の稲の品種や農耕技術では、寒い地域での、耕作は難しいものでした。
その為、現在においても、水田跡が見つかっていない北海道においては「弥生時代」ではなく「縄文時代」と同様に狩猟採集を中心とした生活を送っていた事から「続縄文時代」という時代区分がされています。
かつて、青森県を含む東北地方も「弥生時代」はなく「続縄文時代」という時代区分がされていたのです。
「え!?ピラミッドってお墓じゃないの!?ミイラいるし!!」
「違います。あそこにいる遺体達(ミイラ)は、高度な医療機関がある惑星(ほし)に、送るために置いてあるだけです。」
「この日本には、転送装置が多くあるのに、知らないんですか?」
「無いし!!日本に、ピラミッドなんか無いから!!」
「ありますよ。立派な古墳(ピラミッド)が。」

『ダンダダン』桃とセルポ星人の会話です。
♦かつて東北地方には「弥生時代」はなかったとされていた
かつて、青森県を含む東北地方には「弥生時代はなかった」とされていました。
「弥生時代はなかった」とは「稲作文化は伝わっていなかった」という事です、
しかし、垂柳遺跡での発掘調査において、これまでの日本史の常識が覆ります。
垂柳遺跡から、弥生時代中期の水田遺跡が、検出されたのです。
青森県域において、弥生時代の水田跡が見つかった事で、日本史や農業史は、大きく塗り替えられる事になりました。
水田遺跡は、火山灰層に覆われていた為、保存状態が良好であり、弥生時代を生きていた人々の足跡まで、確認出来ました。
足跡には、大人だけではなく、子どものものもあり、家族総出で稲作をしていた様子が、伺えます。
また、青森県弘前市の砂沢遺跡からは、弥生時代前期の水田跡も、見つかりました。
垂柳遺跡よりも古い時代の水田跡が、さらに北側で発見された事により、青森県域、否、東北地方の弥生時代の始まりが、再考されたのです。
弥生時代前期という、稲作伝来から、然程時間の経っていない時期に、津軽平野には、弥生文化が到達していたのです。
この理由は、1,700年続いた「縄文時代」の「三内丸山遺跡」において、築いてきた広範な交易ネットワークと社会交流を続けてきた為です。
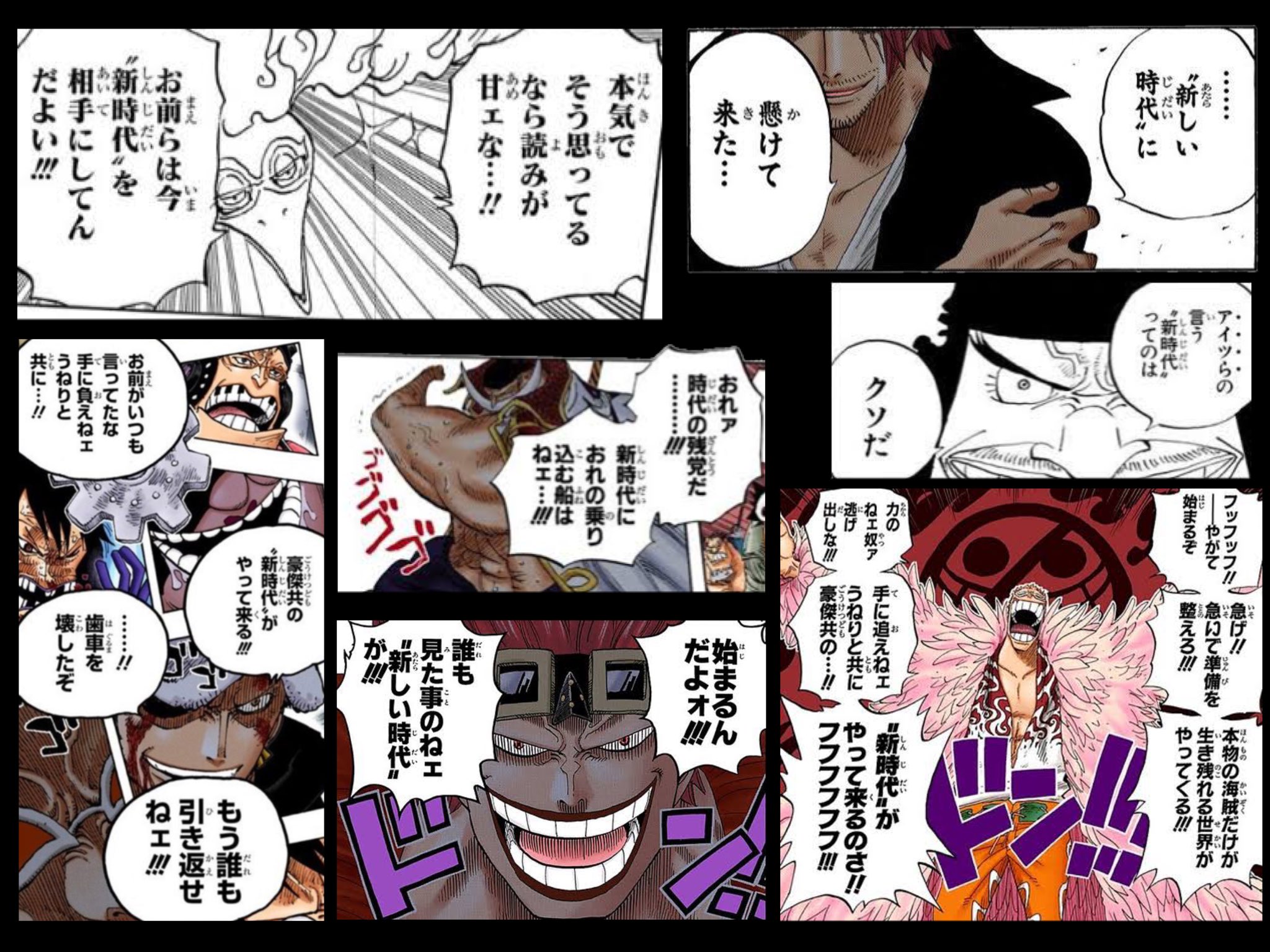
時代は、繋がっている。
実際に時代の舞台に足を運び、学ぶ事で、時代の繋がりを感じる事が出来る事は、何よりもの贅沢です。
…賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶ…
私は、この言葉に、反対です。
人は、経験からしか学ぶ事が出来ない事がある為です。
しかし、経験だけでは、サンプル数が、少ないものです。
経験と歴史、両方から、学ぶ事が大切であると、私は、考えています。
