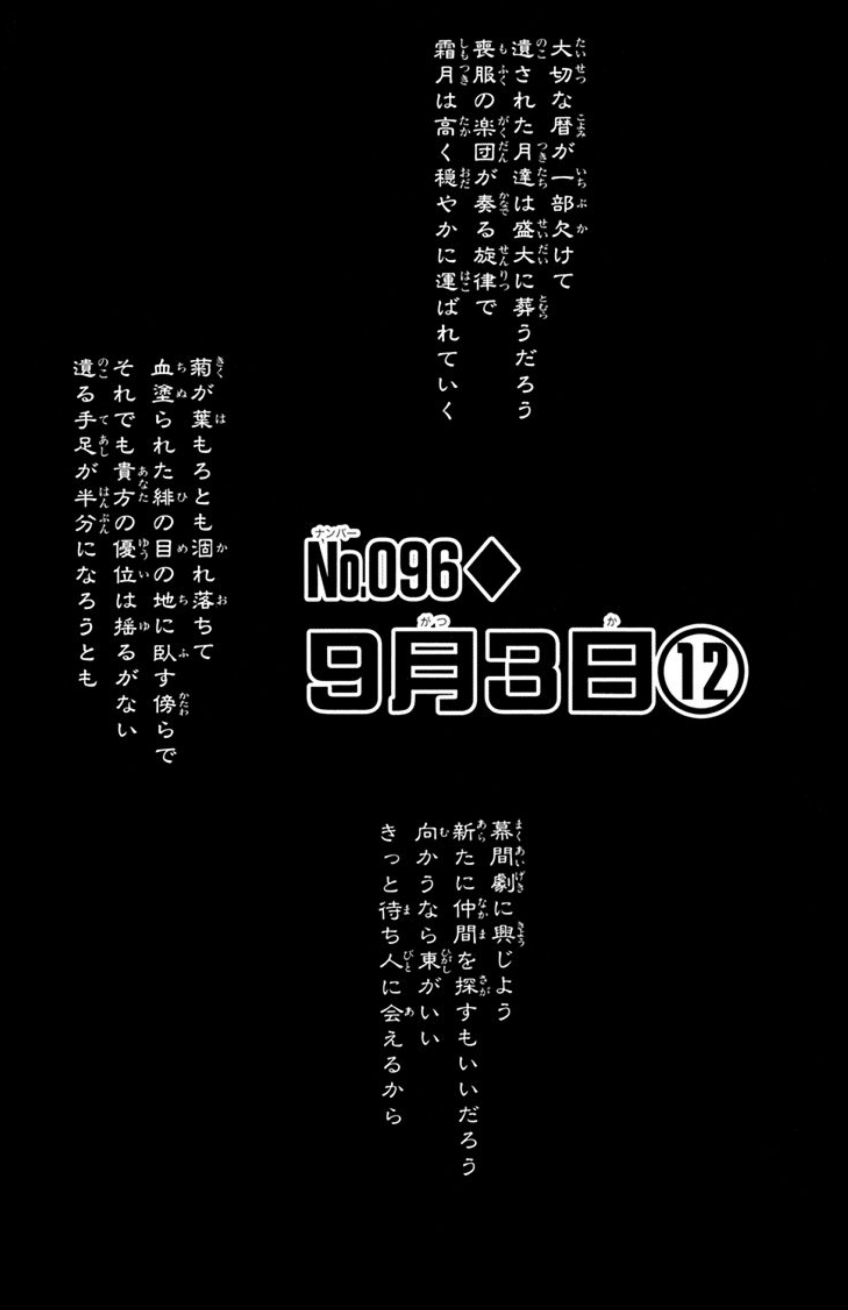「春は夜桜。夏には星。秋には満月。冬には雪。それで十分酒は美味い。」
「それでも不味いんなら、それは自分自身の何かが病んでいる証拠だ。」

『るろうに剣心』比古清十郎の言葉です。
♦大切な暦が一部欠けて、遺された月達が盛大に弔うだろう
二十四節季において、11月7日~11月21日までを「立冬」と呼びます。
紅葉が見頃を迎え、体感的には、最も秋を感じやすい時期ですが、暦の上では冬が始まります。
『HUNTER×HUNTER』好きであれば、11月(霜月)と言えば、上記の占いを思い出す人も、多いのではないでしょうか?
私は『HUNTER×HUNTER』の影響もあり、11月が好きです。
上記の理由以外に、私が11月が好きな理由は、11月が何かを始めるのに最も適した月であるからです。
多くの人は「新年の誓い」に代表されるように、1月から何かを始めようとします。
そして、その始めた何かは大抵の場合、数日から数週間で、終わってしまいます。
ここで、お勧めしたいのが、11月から始める事です。
11月から始める事で、1月には、その何かをする事が、習慣になっています。
勉強においても、仕事においても、人より成果を上げ続けるコツは、人より早く始める事です。
進学校が何故進学校たるかは、通常の学校が、中学校1年生でやる事を小学校6年生で、高校1年生でやる事を中学校3年生でやっているからです。
勿論、勉強が出来るか否か、更には努力を続ける事が出来るか否かの50%以上は、遺伝で決定します。
ただ、そこを抜きにして、進学校側がやっている事といえば、普通の学校より、早めに学習を始める事位です。
何かを始めるのは1月ではなく、11月から。
是非、試してみてください。
♦喪服の楽団が奏でる旋律で、霜月は高く穏やかに運ばれていく
① 起源:古代中国の「二十四節気(にじゅうしせっき)」
-
立冬は、太陽の動きをもとに1年を24の季節に分けた「二十四節気」の一つです。
-
約2300年前、古代中国の「戦国時代」ごろに作られたといわれます。
-
当時の人々は、農業を行うために**太陽の位置(黄道上の度数)**を基準に季節を決めていました。
-
「立冬」は、太陽が黄経225度に達したとき。
-
現代の暦では、だいたい11月7日ごろにあたります。
-
「立」は“はじまる”という意味、
「冬」は“終わり”や“閉じる”を意味し、
「立冬」は“自然が静まり、万物が休みに入る時”を表しています。
② 日本への伝来:奈良時代(8世紀ごろ)
-
日本に二十四節気が伝わったのは、奈良時代(710〜794年)。
当時、中国の暦(太陰太陽暦)を採用していたためです。 -
『日本書紀』や『続日本紀』などの古文書にも、
節気を使った季節の記録が登場します。
日本では農耕の国だったため、
二十四節気は田植え・収穫・冬支度などの目安として重宝されました。
③ 昔の暮らしと立冬
立冬は「冬の始まり」とされ、各地でさまざまな風習がありました。
🌾 農村では
-
収穫を終えて、農具を片づける時期。
-
田畑を休ませ、冬越しの準備を始める節目でした。
🍲 食べものでは
-
冬に備えて味噌・漬物・干物を作り始める時期。
-
「立冬の日に鍋を食べると風邪をひかない」とも言われていました。
🎎 宮中行事では
-
平安時代には、立冬の日に「新しい冬の衣」を着る「更衣(ころもがえ)」の儀が行われました。
-
天皇もこの日に衣を替え、「冬の始め」を正式に宣言していたといわれます。
④ 現代の立冬
-
現代では、気象的な「冬」より少し早い時期に訪れます。
(実際の寒さの始まりは11月下旬〜12月初め)
♦菊が葉もろとも枯れ落ちて、血塗られた緋の目の地に臥す傍らで
「立冬」の旬の食材は、①ごぼう②洋梨③生姜です。
①ごぼうを食用にしている国は、世界において、日本と台湾だけです。
ごぼうと日本人の関りは古よりあり、解毒・解熱・鎮咳等に使う薬草として、中国から日本に伝わります。
平安時代初期には、宮廷の献立に、ごぼうの記述がある為、平安時代初期から、日本ではごぼうを野菜として、食べていました。

現在流通しているごぼうは「滝野川ごぼう」と呼ばれる、根が細くて長いごぼうです。
太さは3㎝程ですが、長さが1mにもなるのが、特徴です。
名の由来は、江戸時代に現在も同様の地名がある東京都北区滝野川から、取られた事に、由来します。
京料理で使われる「堀川ごぼう」は「滝野川ごぼう」を越冬させて、太くさせた品種です。
ごぼうには「食物繊維」が豊富に含まれおり、野菜の中でもトップクラスです。
その為、便秘解消に加え、血糖値・コレステロール値を低下させるのに、ごぼうを食べる事は、効果的です。
②洋梨は「バラ科ナシ属」の樹に実る果実の総称で「西洋梨」や「ラフランス」等とも呼ばれています。
ヨーロッパでは「至福・幸福」中国では「金運・繁栄」をもたらす果物として、縁起の良い果物とされています。
洋梨の栽培に適した気候は、寒冷地域である為、日本においては、山形県や新潟県に定着しました。
特に、山形県は、生産量が日本一であり、山形県産の洋梨は、品質も高く評価されています。

洋梨には「ビタミンC」が多く含まれており、抗酸化作用があります。
「ビタミンC」は、免疫力を高めるほか、肌の健康もサポートしてくれます。
他にも、体内の余分なナトリウム(塩分)を排出する「カリウム」や、骨の健康を支える「ビタミンK」も含まれています。
③生姜は、紀元前2000年頃からインドや中国で栽培されていたとされています。
インドでは「サンスクリット語」で生姜を「シンガバラ」と呼び、神聖な植物とされていました。
インドの伝統医学であるアーユルヴェーダでは、生姜は消化を助け、体を温める作用があるとされ、さまざまな病気の治療に使用されていました。

古くから伝わる様に、生姜には、寒気等の冷えを散らす効果が期待出来ます。
寒気がするような風邪の初期には、生姜をすってお湯に入れ、はちみつや黒砂糖等を加えた生姜湯を、飲む事がお勧めです。
ただし、喉の痛みがある場合は、避けるように。
痛みは炎症である為、温めると悪化するリスクがあります。
食事が、美味しくなる重要な要素は、2つです。
1つは、空腹である事。
もう1つは、旬の食材を味わう事。
旬の食材を味わい、心と身体に栄養を補給して、今日も人生を乗り切っていきましょう。